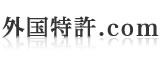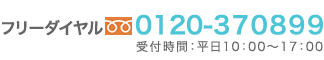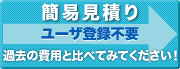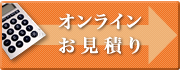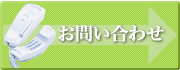外国への特許出願は、日本で出願する場合と異なり、出願する国の現地代理人を介してその国の特許庁へ手続を行う必要がある。出願後には特許庁からの局通知等に現地代理人と関係を密にして対応する必要もある。現地代理人とのやりとりは通常英語であり、また各国の法制は日本と異なることも多く、さらに日本の感覚とは異なる慣行がある国などもあり、そういった点を考慮しながら手続を進めていく。このように外国特許出願は単独ではできず、適切に手続を遂行するための人的ネットワークや経験が重要である。
1.外国で特許出願する意味
日本で特許出願して権利化された特許は、日本の国内だけで有効となる(属地主義)。したがって、日本の特許権に基づいて、外国での行為を日本の特許権の侵害として追求することはできない。日本の特許を有する場合は日本で製造販売される場合に留まらず、国外で製造されたものが日本に輸入されたときにも有効となり、差し止めや損害賠償の請求が可能となる。しかし、外国で製造されたものが日本に入ってこない場合、日本の特許は無力である。外国での行為を追求したい場合は、その国で特許を取得する必要がある。
2.外国で権利を取得するには
外国で特許を取得するには、原則として国ごとに特許出願して権利化を行う必要があり、ひとつを取得すれば全世界共通で通用するような権利は存在しない。外国出願には、「工業所有権の保護に関するパリ条約」に基づく特許出願(いわゆるパリルート)と、「特許協力条約(PCT)」に基づく特許出願(いわゆるPCTルート)とがある。このうちパリルートは、対象国の特許庁にそれぞれ日本の基礎出願から1年以内に特許を出願する。PCTルートは、国際機関に1つの出願を行うことにより多数の国(指定国)へ出願したのと同様の効果を得ることができる。
3.外国出願に必要となる書類と費用
提出書類は、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面の他、国によって異なるが、優先権証明書、現地代理人への委任状(Power of Attorney)などが必要となる。明細書や請求の範囲等は原則としてその国の言語に翻訳して提出する必要があるが、国によっては英語の書類を受け付けたり、また日本語で出願して翻訳文を後日提出したりすることができる。
外国出願時の費用は、各国の特許庁に払うオフィシャルフィー(Official Fee)と、その国の現地代理人に支払うアトーニーフィー(Attorney Fee)の他、現地代理人との仲介を行う国内特許事務所の費用などが必要となる。