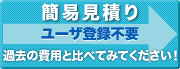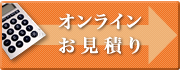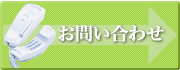出願国の選定
そもそも、外国特許出願は、出願人がどこの国で特許を取得するのが最も有利かを、市場性や優位性、事業の採算性などを考慮して、特許取得に関する経費も勘案しながら出願国を決める。
その上で、先行技術の有無を確認し、特許取得の可能性が高いことを確認したのちに、最終的な出願国を決定する。
PCTを利用することで、国際調査報告により、国内移行先を最終決定する前に関連する先行文献の存在を把握することができるので、無駄な国内移行手続きを未然に防いで、出願コストの削減に寄与することができる。
さらに、日本出願について出願と同時に審査請求した場合、PCT出願の各国移行期限までに日本の審査結果を受け取れる可能性が高い。日本の特許庁は世界的に審査が厳しいと言われており、日本で審査を通れば諸外国でも特許取得の可能性は高いと言える。これらをうまく利用すれば、特許になる可能性の高い出願だけ各国移行へと進めることにより、無駄になる出費を抑えることができる。
こういった外国特許出願の実態から、PCT出願の国内移行まで30ヶ月あるのは、出願人(企業)にとって大きなメリットとなる。
助成金
外国出願を躊躇する大きな要因はやはりその費用にあるだろう。特に外国出願は一般に海外代理人費用とオフィシャルフィーに加え、ハンドリングする日本の特許事務所の費用がかかるため、1つの発明を数カ国に出願するだけで数百万からの費用がかかる。
そんな外国出願を支援するために、中小企業に対し外国出願費用の半分(上限150~300万円)を助成する制度がある。このような支援事業は定期・不定期に様々な自治体が行っており、補助金を受けられる可能性も高く、要件に該当する企業は申請しない手はない。
参考URL
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/3779.html
各国移行の審査にかかる時間
 外国出願(各国移行)を行うと、それぞれの国ごとに審査が行われるが、審査にかかる時間は各国まちまちだ。出願件数が急激に増えている中国やEPが慢性的な審査官不足で5~7年ぐらいかかっている。逆に米国は半年~1年程度と早く、日本と比べて特許になりやすいと言われている。日本は2年程度と速くはないが適切なチェックがされているようだ。
外国出願(各国移行)を行うと、それぞれの国ごとに審査が行われるが、審査にかかる時間は各国まちまちだ。出願件数が急激に増えている中国やEPが慢性的な審査官不足で5~7年ぐらいかかっている。逆に米国は半年~1年程度と早く、日本と比べて特許になりやすいと言われている。日本は2年程度と速くはないが適切なチェックがされているようだ。
外国関連出願の審査を早める特許審査ハイウェイ(PPH)
審査期間を短くしようとする試みとして、PPH(特許審査ハイウェイ)がある。この特許審査ハイウェイは、第1庁(最初に出願した特許庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、申請により、第2庁(他の特許庁)で簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みだ。また、PCT出願の国際調査または国際予備審査で特許性ありと判断された場合に、これを利用する特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)も試行されている。
このようはPPHを利用すれば、例えば日本では現状24~30月かかっている特許審査を約3ヶ月という短期間で審査してもらうことができる。
現在、日本との間でPPHが利用できるのはアメリカ、韓国、イギリスであり、その他ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア、オーストリア、シンガポール、ハンガリー、カナダ、欧州、スペイン、スウェーデン、メキシコ、北欧、中国、ノルウェー、アイスランド、フィリピン、イスラエル、ポルトガル、台湾との間で試行プログラムが運用されている。
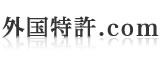
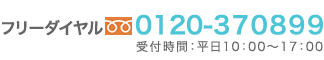

 特許庁 特許審査ハイウェイについて
特許庁 特許審査ハイウェイについて